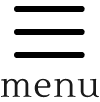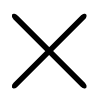新着情報
- 2026-01(2)
- 2025-12(2)
- 2025-09(1)
- 2025-07(3)
- 2025-06(1)
- 2025-05(3)
- 2025-04(2)
- 2025-03(1)
- 2025-02(3)
- 2025-01(2)
- 2024-12(1)
- 2024-10(1)
- 2024-09(1)
- 2024-07(1)
- 2024-06(2)
- 2024-05(4)
- 2024-04(3)
- 2024-03(5)
- 2024-01(3)
- 2023-12(1)
- 2023-10(1)
- 2023-08(2)
- 2023-07(1)
- 2023-06(5)
- 2023-05(1)
- 2023-04(1)
- 2023-03(3)
- 2023-02(5)
- 2023-01(3)
- 2022-12(1)
- 2022-11(1)
- 2022-10(3)
- 2022-09(5)
- 2022-08(9)
- 2022-07(3)
- 2022-06(2)
- 2022-05(3)
- 2022-04(2)
- 2022-03(3)
- 2022-02(3)
- 2022-01(4)
- 2021-12(2)
- 2021-11(2)
- 2021-10(6)
- 2021-09(5)
- 2021-08(4)
- 2021-07(2)
- 2021-06(3)
- 2021-05(5)
- 2021-04(7)
- 2021-03(4)
- 2021-02(8)
- 2021-01(10)
- 2020-12(1)
- 2020-11(5)
- 2020-10(4)
- 2020-09(3)
- 2020-08(6)
- 2020-07(1)
- 2020-06(2)
- 2020-05(6)
- 2020-04(5)
- 2020-03(9)
- 2020-02(8)
- 2020-01(8)
- 2019-12(7)
- 2019-11(8)
- 2019-10(10)
- 2019-09(6)
- 2019-08(4)
- 2019-07(8)
- 2019-06(6)
- 2019-05(2)
2019/07/24
イクメン助成金のご紹介

今回は子育てパパを支援する事業主に対し、支給される助成金のご案内です。
両立支援助成金(出生時両立支援コース)
子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上(大企業14日以上)の父親が育児休業をとった場合、会社に支給されます。連続する5日間には、所定休日が含まれてもOKです
【受給要件】
①平成28年4月1日以降、男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りのために、制度の周知や管理者による育休取得の推奨、また管理者向けの研修のいずれかを実施したこと
②雇用保険被保険者である男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上(大企業14日以上)の育児休業を取得させたこと
③育休制度及び育児のための短時間勤務制度について就業規則または労働協約に規定していること
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定、届出、公表を行なっていること
【受給できる額】
中小企業:取組及び育休取得で 57万円or72万円(その年の1人目施策に支給)
1人目以降10名まで :14.25万円or18万円
![]() 両立支援助成金.pdf (1.3MB)
両立支援助成金.pdf (1.3MB)
詳細はお問い合わせください
つかの社会保険労務士・行政書士事務所
042-453-6295
2019/07/19
キャリアアップ助成金のリーフレット(最新版 抜粋)
有期雇用労働者や派遣労働者を正規雇用労働者等に転換した場合、一定の要件を満たせばキャリアアップ助成金の支給対象となります。要件のひとつに「転換後6ヶ月間の賃金を、転換前6ヶ月間の賃金より5%以上UPさせたこと」というものがあります。この賃金には賞与も含めてOKなのですが、今回、賞与の支給の仕方によっては認められないケースがでてきました。詳細は下記ご参照ください
![]() キャリアアップ助成金__2019.7.pdf (1.59MB)
キャリアアップ助成金__2019.7.pdf (1.59MB)
助成金には、複雑な要件や計画実施のタイミングなど、わかりにくい部分がたくさんあり、本当はもらえるのに諦めてしまっている社長さんも多いです。
ご興味があれば、是非一度ご相談ください。
つかの社会保険労務士・行政書士事務所
042-453-6295
2019/07/15
事務所リーフレット
いつもお世話になっております。
つかの社会保険労務士・行政書士事務所の塚野です。
当事務所のリーフレットと料金表がダウンロードできるようになりました。
是非ご利用ください
![]() 事務所案内.pdf (2.6MB)
事務所案内.pdf (2.6MB)
![]() つかの事務所料金表.pdf (0.78MB)
つかの事務所料金表.pdf (0.78MB)
2019/07/12
東京2020大会に向け「受動喫煙防止対策支援補助金」

健康増進法の一部改正や東京都受動喫煙防止条例にともない、今後、禁煙施設が増えていきます。
東京都では、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、都内の中小飲食店、宿泊施設が行う受動喫煙防止対策を支援する事業を実施しています。2019年1月から実施している経営相談に関する専門家派遣事業に加え、喫煙専用室等の設置に対する補助金の募集がスタート!
■補助対象
・東京都内の飲食店(中小企業、個人事業主の経営によるもの)
・東京都内の宿泊施設
■補助対象事業
①「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置。1施設につき上限400万円
②東京都がH27〜H29年度に実施した「外国人の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境補助金」により整備した分煙設備の撤去等にかかる経費。1施設につき上限150万円
■補助率
客席面積100㎡以下の中小飲食店の場合、補助対象経費の9/10(それ以外の場合は4/5)
詳細は下記サイトをご参照ください
東京都産業労働局観光部受入環境課
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/tourism/kakusyu/syukuhaku/