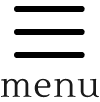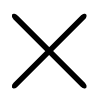新着情報
- 2026-01(2)
- 2025-12(2)
- 2025-09(1)
- 2025-07(3)
- 2025-06(1)
- 2025-05(3)
- 2025-04(2)
- 2025-03(1)
- 2025-02(3)
- 2025-01(2)
- 2024-12(1)
- 2024-10(1)
- 2024-09(1)
- 2024-07(1)
- 2024-06(2)
- 2024-05(4)
- 2024-04(3)
- 2024-03(5)
- 2024-01(3)
- 2023-12(1)
- 2023-10(1)
- 2023-08(2)
- 2023-07(1)
- 2023-06(5)
- 2023-05(1)
- 2023-04(1)
- 2023-03(3)
- 2023-02(5)
- 2023-01(3)
- 2022-12(1)
- 2022-11(1)
- 2022-10(3)
- 2022-09(5)
- 2022-08(9)
- 2022-07(3)
- 2022-06(2)
- 2022-05(3)
- 2022-04(2)
- 2022-03(3)
- 2022-02(3)
- 2022-01(4)
- 2021-12(2)
- 2021-11(2)
- 2021-10(6)
- 2021-09(5)
- 2021-08(4)
- 2021-07(2)
- 2021-06(3)
- 2021-05(5)
- 2021-04(7)
- 2021-03(4)
- 2021-02(8)
- 2021-01(10)
- 2020-12(1)
- 2020-11(5)
- 2020-10(4)
- 2020-09(3)
- 2020-08(6)
- 2020-07(1)
- 2020-06(2)
- 2020-05(6)
- 2020-04(5)
- 2020-03(9)
- 2020-02(8)
- 2020-01(8)
- 2019-12(7)
- 2019-11(8)
- 2019-10(10)
- 2019-09(6)
- 2019-08(4)
- 2019-07(8)
- 2019-06(6)
- 2019-05(2)
2025/05/21
労働保険 年度更新手続のご案内

労働保険の年度更新は、毎年1回、4/1〜3/31の労働者の賃金を集計し、確定保険料および概算保険料を申告書に記載して、都道府県労働局に申告する手続です。
申告期間は、令和7年6月2日(月)〜7月10日(木)となっています。
《手続代行のご案内》
労働保険料申告書の記入方法がわからない、忙しくて作成している時間がないという企業の方、手続きをサポート致します。法改正や複雑な建設業一括有期の申告もご相談ください。
まずはお電話か、お問い合わせフォームからどうぞ
2025/05/21
社会保険 算定基礎届のご案内

会社員や公務員の方は、毎月の給与から、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)が控除されています。社会保険では実際の報酬(給与など)と決定した標準報酬月額に大きな差が生じないよう、年1回、見直しをします。
具体的には4月〜6月に受けた報酬によって算定します。この届出書類を「算定基礎届」といい、今年の提出期限は7月10日(木)です。
業務の性質上、4月〜6月が例年繁忙期で、この3ヶ月の報酬の平均額と年間平均額との間に、2等級以上の差が生じる時は、年平均額で算定することができます。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月分〜翌年8月分まで)の各月に適用され、保険料の計算や将来の年金額等の計算の基礎となります。
《手続代行のご案内》
社会保険の煩雑な手続きは、専門家に依頼すれば時間と手間の大幅な節約になります。
社会保険労務士が、迅速かつ正確な届出はもちろん、「働き方」のアドバイスも致します。
お問い合わせは、つかの社会保険労務士事務所まで
https://tsukano-office.com/contact
2025/04/14
GW中の営業について
いつも大変お世話になっております。つかの社会保険労務士・行政書士事務所です。
ゴールデンウィーク中の営業はカレンダー通りとなりますが、4/30は連絡の取りづらい状況になると思います。
お急ぎの場合は、メールにてご連絡頂ければ順次お返事致します。
https://tsukano-office.com/contact
よろしくお願いします。
2025/04/11
令和7年度 業務改善助成金

令和7年度の業務改善助成金の詳細が発表されました。
詳細は下記ご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
変更点
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
つかの事務所では業務改善助成金の申請サポートをしております。
お気軽にお問い合わせください
2025/03/21
キャリアアップ助成金 変更点のおしらせ
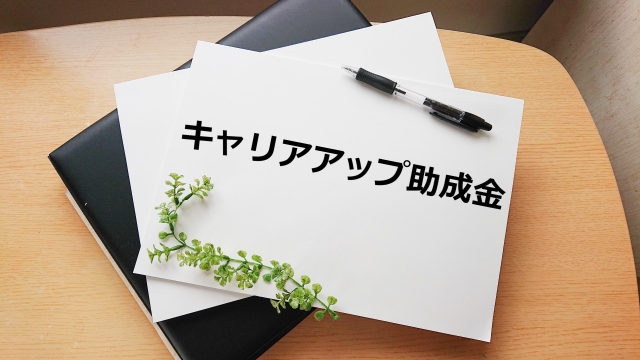
4月1日以降の、キャリアアップ助成金の改正予定をお知らせします。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001450174.pdf
利用を検討されている会社様は要チェックです!
正式発表がありましたら再度ご案内します